継承語に関する研究について紹介しています。日本語に特化した研究以外にも、他の言語の研究なども紹介し、総合的に継承語の維持について考えています。他にも、継承語の研究に関する入門書なども紹介しています。
AG5プロジェクトのウェブサイト
 文部科学省の事業「在外教育施設の高度グローバル人材育成拠点事業」で、高度な(Advanced)グローバル人材(Global human resources)の育成を目的としたAG-5 (https://ag-5.jp)というプロジェクトのウェブサイトの紹介です。 全世界の日本人学校と補習校の支援を目標に、7つのテーマに沿って、先生や研究者の共同研究などをすすめるというプロジェクトで、AG-5とあるのですが、なぜか実際に扱うテーマは以下の7つになっています。 研究テーマ 1.日本人学校における高度グローバル人材の基礎的資質形成のためのプログラム開発 研究テーマ 2.日本人学校における総合学習型日本語力向上プログラムの開発 研究テーマ 3.日本人学校における教員(学校採用教員)の指導力向上のためのプログラム開発 研究テーマ 4.補習授業校における日本語能力向上のための総合的なプログラム開発 研究テーマ 5.日本文化発信の拠点形成プログラム開発 研究テーマ 6.ICTを活用した遠隔での教育の質向上のためのプログラム開発 研究テーマ 7.特別支援教育に関する遠隔指導実施に向けた実践的研究 どちらかと言うと、継承日本語の教育者、研究者向けのウェブサイトですが、非常に多くの研究資料や、教材などのアイデアがあります。基本的には文部科学省のこれまでの指針と同じく、日本帰国予定者向けの補習校への援助と謳っていますが、資料内容とかをみると、どこも補習校は永住者や長期滞在者向け子女の教材開発などがトピックに上がっていました。
文部科学省の事業「在外教育施設の高度グローバル人材育成拠点事業」で、高度な(Advanced)グローバル人材(Global human resources)の育成を目的としたAG-5 (https://ag-5.jp)というプロジェクトのウェブサイトの紹介です。 全世界の日本人学校と補習校の支援を目標に、7つのテーマに沿って、先生や研究者の共同研究などをすすめるというプロジェクトで、AG-5とあるのですが、なぜか実際に扱うテーマは以下の7つになっています。 研究テーマ 1.日本人学校における高度グローバル人材の基礎的資質形成のためのプログラム開発 研究テーマ 2.日本人学校における総合学習型日本語力向上プログラムの開発 研究テーマ 3.日本人学校における教員(学校採用教員)の指導力向上のためのプログラム開発 研究テーマ 4.補習授業校における日本語能力向上のための総合的なプログラム開発 研究テーマ 5.日本文化発信の拠点形成プログラム開発 研究テーマ 6.ICTを活用した遠隔での教育の質向上のためのプログラム開発 研究テーマ 7.特別支援教育に関する遠隔指導実施に向けた実践的研究 どちらかと言うと、継承日本語の教育者、研究者向けのウェブサイトですが、非常に多くの研究資料や、教材などのアイデアがあります。基本的には文部科学省のこれまでの指針と同じく、日本帰国予定者向けの補習校への援助と謳っていますが、資料内容とかをみると、どこも補習校は永住者や長期滞在者向け子女の教材開発などがトピックに上がっていました。「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の閣議決定
 ここや、ここでも紹介しましたが、日本での(非日本語母語話者に対する)日本語教育の制度化が進んでいます。 2019年6月には、「日本語教育の推進に関する法律」が公布、施行されましたが、それに続き、向こう5年間の取り組みを決めた「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が2020年6月23日に閣議決定されたそうです。方針のコピーはhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/pdf/92327601_02.pdfで見られます。 これらの法律の成立過程については、「にほんごぷらっと」の以下の記事が詳しいです。 あと、「日本語教育の推進に関する法律」、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」は、文化庁のこのページに掲載されています。 これらの法案は、主に日本国内で日本語を母語としない人たちへの日本語教育に関する施策なのですが、海外での継承日本語話者に関する項目も含まれています。これらの法律、方策では、「継承日本語」という言葉は使われず、「海外に在留する邦人の子等」への日本語教育という表記になっており、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」では、pp.12-13に記載があります。向こう5年間でどういう施策を行うのかという具体例がいくつか書かれているのですが、まとめると以下のような感じです。 国際交流基金を通じて、継承日本語の教育形態や課題などについての実態把握を行う。また、「現地の日本語教育を行う機関」等と連携しつつ必要な支援を実施する。 教科書の無償給与、教師の派遣、校舎借料などを「在外教育施設」に行う。 中南米地域などには、JICAを通じた支援を行う。 上記の2点目や3点目に関しては、これまでも行われてきたことが書かれているように感じるのですが、国際交流基金の記述に関しては、国際交流基金は、日本語を外国語と学ぶ人への支援をするとということが多かったのですが、「現地の日本語教育を行う機関」で日本語を外国語として学習する学生だけでなく、日本語を継承語として学習する人たちへの支援も行うということで、継承日本語教育に関して少し進展があったように感じます。
ここや、ここでも紹介しましたが、日本での(非日本語母語話者に対する)日本語教育の制度化が進んでいます。 2019年6月には、「日本語教育の推進に関する法律」が公布、施行されましたが、それに続き、向こう5年間の取り組みを決めた「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が2020年6月23日に閣議決定されたそうです。方針のコピーはhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/pdf/92327601_02.pdfで見られます。 これらの法律の成立過程については、「にほんごぷらっと」の以下の記事が詳しいです。 あと、「日本語教育の推進に関する法律」、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」は、文化庁のこのページに掲載されています。 これらの法案は、主に日本国内で日本語を母語としない人たちへの日本語教育に関する施策なのですが、海外での継承日本語話者に関する項目も含まれています。これらの法律、方策では、「継承日本語」という言葉は使われず、「海外に在留する邦人の子等」への日本語教育という表記になっており、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」では、pp.12-13に記載があります。向こう5年間でどういう施策を行うのかという具体例がいくつか書かれているのですが、まとめると以下のような感じです。 国際交流基金を通じて、継承日本語の教育形態や課題などについての実態把握を行う。また、「現地の日本語教育を行う機関」等と連携しつつ必要な支援を実施する。 教科書の無償給与、教師の派遣、校舎借料などを「在外教育施設」に行う。 中南米地域などには、JICAを通じた支援を行う。 上記の2点目や3点目に関しては、これまでも行われてきたことが書かれているように感じるのですが、国際交流基金の記述に関しては、国際交流基金は、日本語を外国語と学ぶ人への支援をするとということが多かったのですが、「現地の日本語教育を行う機関」で日本語を外国語として学習する学生だけでなく、日本語を継承語として学習する人たちへの支援も行うということで、継承日本語教育に関して少し進展があったように感じます。「日本語教育の推進に関する法律」関するフォーラム @ Boston
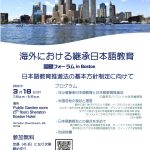 先日、日本で制定された「日本語教育の推進に関する法律」がどのように海外での継承日本語話者の教育に影響があるのかを議論するフォーラムが、AATJ (全米日本語教育学会)のJapanese as a Heritage Languageの部会主宰で2020年3月18日(水)にボストンで開催されるそうです。詳細は、以下の通りです。参加無料ですが登録が必要で、定員が45名となっていますので、早めに登録ください。 ---------------------------------- 海外における継承日本語教育の充実に向けて ---------------------------------- 日程: 2020年 3月18日(水) 時間: 7:30pm-9:30pm 場所: Public Garden room (5th floor) Sheraton ...
先日、日本で制定された「日本語教育の推進に関する法律」がどのように海外での継承日本語話者の教育に影響があるのかを議論するフォーラムが、AATJ (全米日本語教育学会)のJapanese as a Heritage Languageの部会主宰で2020年3月18日(水)にボストンで開催されるそうです。詳細は、以下の通りです。参加無料ですが登録が必要で、定員が45名となっていますので、早めに登録ください。 ---------------------------------- 海外における継承日本語教育の充実に向けて ---------------------------------- 日程: 2020年 3月18日(水) 時間: 7:30pm-9:30pm 場所: Public Garden room (5th floor) Sheraton ...MiiPro Corpus: 日本語母語話者の言語発達サンプル (1歳から5歳)
 継承日本語話者の子女を育てていると、自分の子供の日本語能力が、日本語を母語として獲得している子供たちと比べてどの程度の発達レベルなのかと気になることがあります。日本に頻繁に一時帰国している場合などは、他の家庭の子女との交流などから、自分の子供の継承日本語のレベルなどがわかるのかもしれませんが、そんなに頻繁に一時帰国できるものでもないですし、なかなか自分の子供の日本語のレベルが、日本語母語話者と比べてどの程度の遅れがあるのかはわかりづかいものです。 で、そういった際に使いやすいのが、CHILDESという言語習得研究者用のデーターベースです。もともとは、Carnegie Mellon UniversityのBrian MacWhinney氏が、自分の子供の言語発達を1970年代に音声録音したものを書き起こし(テキスト化)し、研究用に公開したのが始まりなのですが、そこから世界中の研究者が同様なデータベースを共有し始めて、英語だけでなく、いろいろな言語を母語とする子供たちの言語発達データベースになりました。 第一言語習得の研究者の中では必須のデータベースですが、一般に無料で公開されています。日本語では、愛知淑徳大学の宮田Susanne先生が率先して日本語のCHILDESデータベースを構築されています (ワークショップの資料などがこのページで公開されています)。 その宮田Susanne先生が編纂したCHILDESデータベースで、MiiPro Corpusというものがあります。1歳から5歳の、日本語を母語とする子供の音声記録をオンラインで聞くことができます。 Go to https://childes.talkbank.org/access/Japanese/MiiPro.html Click on "Browsable transcripts" Click on child's name 言語形態学的な情報などがあり、ちょっとスクリプトは見にくいですが、音声を聞くだけでも、「ああ、日本の母語話者は、この年でこの程度の日本語を話すんだ」というイメージが掴めると思います。よく話す子、あまり話さない子などの違いはありますが、言語学的な視点から見ると、日本語の母語発達も年齢と非常に比例して規則的に発達しています。
継承日本語話者の子女を育てていると、自分の子供の日本語能力が、日本語を母語として獲得している子供たちと比べてどの程度の発達レベルなのかと気になることがあります。日本に頻繁に一時帰国している場合などは、他の家庭の子女との交流などから、自分の子供の継承日本語のレベルなどがわかるのかもしれませんが、そんなに頻繁に一時帰国できるものでもないですし、なかなか自分の子供の日本語のレベルが、日本語母語話者と比べてどの程度の遅れがあるのかはわかりづかいものです。 で、そういった際に使いやすいのが、CHILDESという言語習得研究者用のデーターベースです。もともとは、Carnegie Mellon UniversityのBrian MacWhinney氏が、自分の子供の言語発達を1970年代に音声録音したものを書き起こし(テキスト化)し、研究用に公開したのが始まりなのですが、そこから世界中の研究者が同様なデータベースを共有し始めて、英語だけでなく、いろいろな言語を母語とする子供たちの言語発達データベースになりました。 第一言語習得の研究者の中では必須のデータベースですが、一般に無料で公開されています。日本語では、愛知淑徳大学の宮田Susanne先生が率先して日本語のCHILDESデータベースを構築されています (ワークショップの資料などがこのページで公開されています)。 その宮田Susanne先生が編纂したCHILDESデータベースで、MiiPro Corpusというものがあります。1歳から5歳の、日本語を母語とする子供の音声記録をオンラインで聞くことができます。 Go to https://childes.talkbank.org/access/Japanese/MiiPro.html Click on "Browsable transcripts" Click on child's name 言語形態学的な情報などがあり、ちょっとスクリプトは見にくいですが、音声を聞くだけでも、「ああ、日本の母語話者は、この年でこの程度の日本語を話すんだ」というイメージが掴めると思います。よく話す子、あまり話さない子などの違いはありますが、言語学的な視点から見ると、日本語の母語発達も年齢と非常に比例して規則的に発達しています。U.S. Frontlineのバイリンガル教育に関する記事
 U.S. Frontlineの2019年10月号に、「押さえておきたいバイリンガル教育のカギ」 (https://usfl.com/2019/09/post/125387) という特集が組まれていました。日本語バイリンガル教育に従事している方々が、それぞれの分野において日本語と英語のバイリンガル教育に関する注意点を書かれたものです。どちらかというと、アメリカ長期滞在者(永住組)向けに書かれたもののようですが、最後の方には、日本に帰国した際の学校選びについても書かれてあり、どのようなバックグラウンドでのバイリンガル教育を考えているのかとか、場所的にもU.S. Frontlineさんが全国紙のためか、いろいろな場所を考慮したという感じの内容です。それぞれの個々の事情に対した情報というよりも、全般的な導入的な情報という感じですので、いまから子供さんをバイリンガルに育てていくという家庭の方にはオススメです。
U.S. Frontlineの2019年10月号に、「押さえておきたいバイリンガル教育のカギ」 (https://usfl.com/2019/09/post/125387) という特集が組まれていました。日本語バイリンガル教育に従事している方々が、それぞれの分野において日本語と英語のバイリンガル教育に関する注意点を書かれたものです。どちらかというと、アメリカ長期滞在者(永住組)向けに書かれたもののようですが、最後の方には、日本に帰国した際の学校選びについても書かれてあり、どのようなバックグラウンドでのバイリンガル教育を考えているのかとか、場所的にもU.S. Frontlineさんが全国紙のためか、いろいろな場所を考慮したという感じの内容です。それぞれの個々の事情に対した情報というよりも、全般的な導入的な情報という感じですので、いまから子供さんをバイリンガルに育てていくという家庭の方にはオススメです。Community-Based Heritage Language Schools Conference (Sat, Oct 12, 2019)
 毎年、Washington D.C.のAmerican Universityで行われている継承語教育に関するCommunity-Based Heritage Language Schools Conference (https://www.american.edu/soe/iie/heritage-language-conference.cfm)という学会がSaturday, October 12, 2019に開催されます。 日本語を含む、様々な言語の継承語学校の関係者(教員や運営者など)が集まる珍しい学会です。個人による発表がなく、どちらかというとワークショップに近い感じがしますが、それぞれの継承語学校がどのような環境で、どのような教育を行っているのかという情報交換ができるとてもよい集まりです。特に、アメリカの継承語教育に関わる全米組織の役員の人たちが来るので、それぞれの組織が継承語教育に対してどのようなサポートをしているのかというのがわかります。2019年に参加する団体は、以下の通りです。 Center for Applied Linguistics (CAL) National ...
毎年、Washington D.C.のAmerican Universityで行われている継承語教育に関するCommunity-Based Heritage Language Schools Conference (https://www.american.edu/soe/iie/heritage-language-conference.cfm)という学会がSaturday, October 12, 2019に開催されます。 日本語を含む、様々な言語の継承語学校の関係者(教員や運営者など)が集まる珍しい学会です。個人による発表がなく、どちらかというとワークショップに近い感じがしますが、それぞれの継承語学校がどのような環境で、どのような教育を行っているのかという情報交換ができるとてもよい集まりです。特に、アメリカの継承語教育に関わる全米組織の役員の人たちが来るので、それぞれの組織が継承語教育に対してどのようなサポートをしているのかというのがわかります。2019年に参加する団体は、以下の通りです。 Center for Applied Linguistics (CAL) National ...子供をバイリンガルに育てるメリットとデメリット
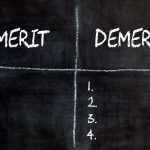 前学期に教えていたクラスで、アメリカで子供をバイリンガルに育てるメリットとデメリットをまとめるプロジェクトをしたので、それのまとめを日本語で書いておこうと思いました。バイリンガルのメリットとデメリットについて、科学的に実証されている、あるいは客観的に記載されている事実についてをまとめようというプロジェクトでしたが、研究で確立している事象だけを考えると、バイリンガルのメリットは非言語的な認知力についてのものが多く、デメリットは言語的なものが多かったのがおもしろかったです。 バイリンガルのメリット 言語に関するメタ知識(言語をコミュニケーションのシステムとして認知する知識)が高く、言語に対する反応がモノリンガルと異なる。例えば、"Which is more like CAP? CAN or HAT?"という質問があると、モノリンガルの英語話者は、音声的に近いCANを選ぶことが多いが、バイリンガル話者は、HATも意味的に近いと答える。 クリエイティビティーが高い。例えば、"Tell me all the things you could do ...
前学期に教えていたクラスで、アメリカで子供をバイリンガルに育てるメリットとデメリットをまとめるプロジェクトをしたので、それのまとめを日本語で書いておこうと思いました。バイリンガルのメリットとデメリットについて、科学的に実証されている、あるいは客観的に記載されている事実についてをまとめようというプロジェクトでしたが、研究で確立している事象だけを考えると、バイリンガルのメリットは非言語的な認知力についてのものが多く、デメリットは言語的なものが多かったのがおもしろかったです。 バイリンガルのメリット 言語に関するメタ知識(言語をコミュニケーションのシステムとして認知する知識)が高く、言語に対する反応がモノリンガルと異なる。例えば、"Which is more like CAP? CAN or HAT?"という質問があると、モノリンガルの英語話者は、音声的に近いCANを選ぶことが多いが、バイリンガル話者は、HATも意味的に近いと答える。 クリエイティビティーが高い。例えば、"Tell me all the things you could do ...新時代海外移住者の日本語継承
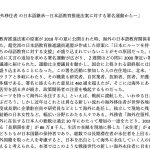 カルダー, 淑子. (2019). 新時代海外移住者の日本語継承: 日本語教育推進法案に対する署名運動から. In 喬. 宮島 et al. (Eds.), 開かれた移民社会へ. ...
カルダー, 淑子. (2019). 新時代海外移住者の日本語継承: 日本語教育推進法案に対する署名運動から. In 喬. 宮島 et al. (Eds.), 開かれた移民社会へ. ...日本語の国語教育(学習指導要領)と継承語教育への子女と保護者の反応
 Doerr, N. M. & Lee, K. (2009). Contesting heritage: language, legitimacy, and schooling at a ...
Doerr, N. M. & Lee, K. (2009). Contesting heritage: language, legitimacy, and schooling at a ...オレンジコースト学園の継承語カリキュラムへの移行過程
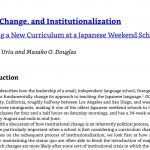 Uriu, R. M. & Douglas, M. O. (2017). Crisis, Change, and Institutionalization: Adopting a New ...
Uriu, R. M. & Douglas, M. O. (2017). Crisis, Change, and Institutionalization: Adopting a New ...