継承語に関する研究について紹介しています。日本語に特化した研究以外にも、他の言語の研究なども紹介し、総合的に継承語の維持について考えています。他にも、継承語の研究に関する入門書なども紹介しています。
PBSのドキュメンタリーAsian Americansの無料公開
 5月がAAPI Monthのためだと思うのですが、PBSが作ったドキュメンタリーのAsian Americansがオンラインで無料公開されています。 1時間の5つのエピソードがあり、アジア系アメリカ人の歴史について紹介されています。日系アメリカ人の歴史について深く書かれているのは、Episodes 2-3で、Episode 2では、第二次世界大戦中に日系人強制収容所に収容された日系アメリカ人たちが「アメリカの兵役に就くかどうか」、「日本の天皇には忠誠を誓わないか」などの質問をされ、その答えによって、家族がばらばらにされてしまった歴史などが紹介されています。Episode 3では、第二次世界大戦後に"Model Minority"とあだ名されて、アジア人は白人社会にとって脅威であるとメディアで報道されて迫害されるアジア人の歴史を紹介しています。 10歳になった自分の子供と見たのですが、学校でもある程度、アメリカの歴史を勉強しているので、いろいろ質問されました。たぶん、子供と見るのであれば、最初に自分だけで見て、わからないところなどは事前に調べておいた方がよいかもしれません。上記のサイトでは、教育用の解説資料やその他のリソースも見ることができるようです。 以下、それぞれのエピソードの解説です。 Episode 1 - Breaking Ground: In an era of ...
5月がAAPI Monthのためだと思うのですが、PBSが作ったドキュメンタリーのAsian Americansがオンラインで無料公開されています。 1時間の5つのエピソードがあり、アジア系アメリカ人の歴史について紹介されています。日系アメリカ人の歴史について深く書かれているのは、Episodes 2-3で、Episode 2では、第二次世界大戦中に日系人強制収容所に収容された日系アメリカ人たちが「アメリカの兵役に就くかどうか」、「日本の天皇には忠誠を誓わないか」などの質問をされ、その答えによって、家族がばらばらにされてしまった歴史などが紹介されています。Episode 3では、第二次世界大戦後に"Model Minority"とあだ名されて、アジア人は白人社会にとって脅威であるとメディアで報道されて迫害されるアジア人の歴史を紹介しています。 10歳になった自分の子供と見たのですが、学校でもある程度、アメリカの歴史を勉強しているので、いろいろ質問されました。たぶん、子供と見るのであれば、最初に自分だけで見て、わからないところなどは事前に調べておいた方がよいかもしれません。上記のサイトでは、教育用の解説資料やその他のリソースも見ることができるようです。 以下、それぞれのエピソードの解説です。 Episode 1 - Breaking Ground: In an era of ...日系一世移民対象の研究参加者募集
 カリフォルニア臨床心理大学院(アライアント国際大学)の博士学生に在籍されている谷澤香さんという方が、日系一世移民対象の研究を行っており、対象者を募集しているそうです。おそらく、継承日本語話者の保護者の方は対象になるのかと思います。詳しくは、以下の案内を参照ください。
カリフォルニア臨床心理大学院(アライアント国際大学)の博士学生に在籍されている谷澤香さんという方が、日系一世移民対象の研究を行っており、対象者を募集しているそうです。おそらく、継承日本語話者の保護者の方は対象になるのかと思います。詳しくは、以下の案内を参照ください。ニューヨークでの継承日本語教室/学校運営の課題と問題
 Coalition of Community-based Heritage Language Schools (https://www.heritagelanguageschools.org/coalition)という会合で、 全米の継承日本語教室/学校全体でネットワークを作り、継承語教育に関する情報共有やリソースのシェアができないかという話に参加しました。まだまだ理想論で、実現は難しいなぁと感じたのですが、他方で、多くの継承日本語教室/学校が同様な問題や課題に直面しているというのは本当だと思いました。 そこで、かなり主観的な意見ですが、自分の知るニューヨーク近郊の継承日本語教室/学校に関して共有されているであろう問題や課題についてまとめてみました。 資金 ニューヨークでの継承日本語教室/学校を運営する上で最初に直面する問題は、どのように資金を調達するかだと思います。おおまかに分けて、保護者主体で (主に学齢期前の子供たちのために) 日本語による保育を行おうというインフォーマルな日本語教室のパターンと、組織として日本語教室/学校を始めようとするパターンがあるかと思います。 まず、保護者主体で (主に学齢期前の子供たちのために) 日本語による保育を行おうというインフォーマルな日本語教室のパターンです。よくあるのが、1-3歳くらいの学齢期以前の子供を持つ日本語話者の保護者が、公園やその他の地域の集まりなどで知り合いになり、日本語による保育の必要性を話し合った結果、インフォーマルな日本語による保育活動が始まるというケースです。大体、5-6家庭の保護者間で始まり、最終的に20-30家庭くらいまで行くこともあるようですが、このようなインフォーマルな会合ですと、一切お金を徴収せずに、定期的に保護者主体で無料で利用できるような図書館、教会、公園などの施設で集まって日本語を使った活動をするということはよく見られます。ある程度、組織的に日本語活動をするグループですと、場所や先生の為に費用がかかるので、活動ごとに費用を徴収していることもあります。全体的に、規模も小さく、必要な経費も、場所や先生への謝礼など実費だけですので、このパターンでは、資金はそれほど大きな問題にはなりません。 ある程度定期的に会合が開かれたり、保護者間でのネットワークが強まり、しっかりとした組織として日本語教室/学校を始めようと考えると、資金源が非常に大きな問題になります。組織として日本語教室/学校を運営するには、その地域の法律上で幼児教育や保育に必要とされる最低限の設備や事務的機能が必要になってくるので、学校の運営実費だけでなく、その他諸々の経費がかかり、インフォーマルな会合とは桁違いの経費が必要になってきます。例えば、インフォーマルな会合では必要とされなかった、事務職員の給与、保険費、賃貸料、法律上求められる安全設備の購入、先生への謝礼にかかる税金の処理など多くの事務費などが大きな支出になります。組織によってどの程度事務費にお金がかかるかは変わってくると思いますが、以前聞いた話では、ある教室では保護者から徴収した50%以上の収入が、実際の保育とはあまり関係のない事務費にかかると言っていました。 現実的に組織的に日本語教室/学校を始めるにはかなりの費用がかかるので、多くのインフォーマルな日本語教室は、対象子女が学齢期になったり、保護者が仕事を再開したり、引っ越しなどでバラバラになったりして自然解散することが多いです。ですが、時折、インフォーマルなネットワークから組織的な日本語教室/学校になるケースもあります。これまでニューヨークであったケースでは、継承日本語教育に興味のある財団などからの資金調達したパターン(非常にまれ)や既存の公立学校や非営利団体などの一部として継承日本語教育を継続するパターン(結構多い)などがあると思います。よく、資金調達の際に、国際交流基金や日本大使館/総領事館からなどの日本政府系の資金を模索することが多いようですが、継承語教育に対する日本政府からの支援は非常に複雑で、インフォーマルなネットワークを組織的な日本語教室/学校にするために国際交流基金や日本大使館/総領事館が資金的支援をしたというのは例がありません。 人材 継承日本語教室/学校を運営する上で人材はとても大事です。一番大変なのが、長年同じ教室や学校で勤務する人が少なく、知識やノウハウの蓄積ができないことが挙げられます。 継承日本語教室/学校で大事な人材は二種類あり、おおまかに、学校運営や広報などに長けた事務方の人材、日本語教育などの専門知識のある教師の人材が重要になってきます。「全部自分がやれます。」のようなすごい人も時折いるかと思いますが、自分が知っている中で、有能な事務の方が良い先生であったり、良い先生が組織の運営に長けているということはあまり見たことがありません。 有能な事務の方は、経理や法律などに詳しく、学校の場所の確保や、新しい学生の勧誘などに必要なネットワーク設定、コミュニケーション能力に長けた人です。あくまで自分の個人的意見ですが、事務の人は、継承日本語教育に対して自分の理想やあってそれを実践しようとする人よりも、自分の理想は前に出さず、それよりも、教員、保護者、子女が持つさまざまな継承日本語教育に対する理想や目標をうまく聞き出して理解し、それを調整して実現するような人の方がうまく行っている気がします。組織の運営に関しても、みんなが素晴らしいと思う理想論よりも、つまらないけれども現実的な選択ができる人の方が事務的には優れていると感じます。 先生は、当然ながら、継承日本語教育の経験があり、教育の理想や信念がある人が良いです。これも個人的な意見ですが、継承日本語教育に関しては、先生は経験よりも教育信念が高い人の方が向いていると思います。継承日本語教育は、子どものバックグラウンドや日本語能力もさまざまで、普通の日本語教育よりも過去の経験が反映できるという機会が少ないです。10年以上継承日本語教育を教えているような先生であれば別ですが、過去に数年教員経験があるというような経験はあまり継承日本語教育の現場では経験は関係ないと思います。それよりも、継承日本語教育の現場は、いろんな課題や問題が多いので、理想や信念があり、問題に直面してもへこたれたり、辞めてしまったりしないような先生のほうが現場には向いていると感じます。 事務方の人材、先生ともに、継承日本語教室/学校での最大の課題は継続性が低いことです。殆どの継承日本語教室/学校の関係者の方は、数年で職場を離れてしまうので、教室/学校の運営や教育方法のノウハウなどが引き継がれていないことが多くあります。上手く運営できている教室/学校などは、何名かの事務や先生が非常に長期間にわたり勤務されているところが多いです。 場所 場所は、都市部で教室/学校運営しようと思うと非常に重要な問題になってきます。インフォーマルな集まりであれば、誰かの家でやったりとか、教会や図書館など無料でスペースを貸し出ししてくれるところを見つけ、そこで集まったりすることなどができるのですが、 正式に教室や学校として運営しようとするのであれば、長期間にわたってどの場所で教育を行うのかということが確定しないと、NPOの申請、法律上必要な住所の登録、新しい学生の募集や先生の指導プランなど多くの支障が出てきます。ですので、ある程度お金を払っても、1年間を通じて場所が使えるというところを確保する必要が出てくるのです。 継承日本語教育で場所の確保が難しい理由として、1つは既存の学校設備を持った組織が継承日本語をやるということが少ないと言うことにあります。日本政府による日本人学校で教育設備を持っているというケース以外は、継承日本語の教室/学校を始めるには、週末あるいは放課後にだけ、どこかの他の学校や教育施設で場所を確保しなければなりません。既存の学校にコンタクトし、週末だけあるいは放課後だけスペースを借りるというのが、かなり大変で、かなりのお金を払っても長期間、週末だけキャンパスを貸し出してくれる学校や施設はそれほど多くありません。たまたま見つかっても、場所のレンタルの謝礼がネックになったり、突然、スペースが利用ができなくなったりするということもよくあるので、場所に翻弄されることは多いです。また、正式に教室や学校運営しようとすると、それぞれの地域の法律上、子供の安全や、教育設備等が法律によって決められていることもあり、そのような法律を準拠する設備がないので、結局利用できないということもあります。 最も良い場所は、当然、日系人がたくさん住んでいる居住地の近くがいいのですが、既存の継承日本語教室/学校との距離、電車やハイウェイなど通学手段の距離、謝礼の額など、多くの要素があり、なかなか上手く理想の場所に教室/学校が確保できるということは少ないようです。 カリキュラムと教材 カリキュラムに関しては、いろいろ違ったレベルでの課題があります。 ひとつは、インフォーマルな教室や学校では、教育関係の知識が持つ人がいないことがあるので、カリキュラムというコンセプトが無いと言うこともよくあります。 年間のスケジュールがあったり、いろんな行事やイベントの予定はあったりしても、クラスの中でどのような教育を行うのか、そしてその教育の効果をどのように評価するのかなど、カリキュラムの基本的なことが確立されていない事は、インフォーマルな集まりでは往々にあります。インフォーマルな集まりだと、長期的な計画等ができないという理由はあると思いますが、規模を大きくしたり、長期的に存続しようとするのであれば、カリキュラムは非常に大事になってきます。 カリキュラムのもう一つの問題としては、 日本の学習指導要領による教育と継承日本語のカリキュラムという二種類のカリキュラムがあることが挙げられます。 ...
Coalition of Community-based Heritage Language Schools (https://www.heritagelanguageschools.org/coalition)という会合で、 全米の継承日本語教室/学校全体でネットワークを作り、継承語教育に関する情報共有やリソースのシェアができないかという話に参加しました。まだまだ理想論で、実現は難しいなぁと感じたのですが、他方で、多くの継承日本語教室/学校が同様な問題や課題に直面しているというのは本当だと思いました。 そこで、かなり主観的な意見ですが、自分の知るニューヨーク近郊の継承日本語教室/学校に関して共有されているであろう問題や課題についてまとめてみました。 資金 ニューヨークでの継承日本語教室/学校を運営する上で最初に直面する問題は、どのように資金を調達するかだと思います。おおまかに分けて、保護者主体で (主に学齢期前の子供たちのために) 日本語による保育を行おうというインフォーマルな日本語教室のパターンと、組織として日本語教室/学校を始めようとするパターンがあるかと思います。 まず、保護者主体で (主に学齢期前の子供たちのために) 日本語による保育を行おうというインフォーマルな日本語教室のパターンです。よくあるのが、1-3歳くらいの学齢期以前の子供を持つ日本語話者の保護者が、公園やその他の地域の集まりなどで知り合いになり、日本語による保育の必要性を話し合った結果、インフォーマルな日本語による保育活動が始まるというケースです。大体、5-6家庭の保護者間で始まり、最終的に20-30家庭くらいまで行くこともあるようですが、このようなインフォーマルな会合ですと、一切お金を徴収せずに、定期的に保護者主体で無料で利用できるような図書館、教会、公園などの施設で集まって日本語を使った活動をするということはよく見られます。ある程度、組織的に日本語活動をするグループですと、場所や先生の為に費用がかかるので、活動ごとに費用を徴収していることもあります。全体的に、規模も小さく、必要な経費も、場所や先生への謝礼など実費だけですので、このパターンでは、資金はそれほど大きな問題にはなりません。 ある程度定期的に会合が開かれたり、保護者間でのネットワークが強まり、しっかりとした組織として日本語教室/学校を始めようと考えると、資金源が非常に大きな問題になります。組織として日本語教室/学校を運営するには、その地域の法律上で幼児教育や保育に必要とされる最低限の設備や事務的機能が必要になってくるので、学校の運営実費だけでなく、その他諸々の経費がかかり、インフォーマルな会合とは桁違いの経費が必要になってきます。例えば、インフォーマルな会合では必要とされなかった、事務職員の給与、保険費、賃貸料、法律上求められる安全設備の購入、先生への謝礼にかかる税金の処理など多くの事務費などが大きな支出になります。組織によってどの程度事務費にお金がかかるかは変わってくると思いますが、以前聞いた話では、ある教室では保護者から徴収した50%以上の収入が、実際の保育とはあまり関係のない事務費にかかると言っていました。 現実的に組織的に日本語教室/学校を始めるにはかなりの費用がかかるので、多くのインフォーマルな日本語教室は、対象子女が学齢期になったり、保護者が仕事を再開したり、引っ越しなどでバラバラになったりして自然解散することが多いです。ですが、時折、インフォーマルなネットワークから組織的な日本語教室/学校になるケースもあります。これまでニューヨークであったケースでは、継承日本語教育に興味のある財団などからの資金調達したパターン(非常にまれ)や既存の公立学校や非営利団体などの一部として継承日本語教育を継続するパターン(結構多い)などがあると思います。よく、資金調達の際に、国際交流基金や日本大使館/総領事館からなどの日本政府系の資金を模索することが多いようですが、継承語教育に対する日本政府からの支援は非常に複雑で、インフォーマルなネットワークを組織的な日本語教室/学校にするために国際交流基金や日本大使館/総領事館が資金的支援をしたというのは例がありません。 人材 継承日本語教室/学校を運営する上で人材はとても大事です。一番大変なのが、長年同じ教室や学校で勤務する人が少なく、知識やノウハウの蓄積ができないことが挙げられます。 継承日本語教室/学校で大事な人材は二種類あり、おおまかに、学校運営や広報などに長けた事務方の人材、日本語教育などの専門知識のある教師の人材が重要になってきます。「全部自分がやれます。」のようなすごい人も時折いるかと思いますが、自分が知っている中で、有能な事務の方が良い先生であったり、良い先生が組織の運営に長けているということはあまり見たことがありません。 有能な事務の方は、経理や法律などに詳しく、学校の場所の確保や、新しい学生の勧誘などに必要なネットワーク設定、コミュニケーション能力に長けた人です。あくまで自分の個人的意見ですが、事務の人は、継承日本語教育に対して自分の理想やあってそれを実践しようとする人よりも、自分の理想は前に出さず、それよりも、教員、保護者、子女が持つさまざまな継承日本語教育に対する理想や目標をうまく聞き出して理解し、それを調整して実現するような人の方がうまく行っている気がします。組織の運営に関しても、みんなが素晴らしいと思う理想論よりも、つまらないけれども現実的な選択ができる人の方が事務的には優れていると感じます。 先生は、当然ながら、継承日本語教育の経験があり、教育の理想や信念がある人が良いです。これも個人的な意見ですが、継承日本語教育に関しては、先生は経験よりも教育信念が高い人の方が向いていると思います。継承日本語教育は、子どものバックグラウンドや日本語能力もさまざまで、普通の日本語教育よりも過去の経験が反映できるという機会が少ないです。10年以上継承日本語教育を教えているような先生であれば別ですが、過去に数年教員経験があるというような経験はあまり継承日本語教育の現場では経験は関係ないと思います。それよりも、継承日本語教育の現場は、いろんな課題や問題が多いので、理想や信念があり、問題に直面してもへこたれたり、辞めてしまったりしないような先生のほうが現場には向いていると感じます。 事務方の人材、先生ともに、継承日本語教室/学校での最大の課題は継続性が低いことです。殆どの継承日本語教室/学校の関係者の方は、数年で職場を離れてしまうので、教室/学校の運営や教育方法のノウハウなどが引き継がれていないことが多くあります。上手く運営できている教室/学校などは、何名かの事務や先生が非常に長期間にわたり勤務されているところが多いです。 場所 場所は、都市部で教室/学校運営しようと思うと非常に重要な問題になってきます。インフォーマルな集まりであれば、誰かの家でやったりとか、教会や図書館など無料でスペースを貸し出ししてくれるところを見つけ、そこで集まったりすることなどができるのですが、 正式に教室や学校として運営しようとするのであれば、長期間にわたってどの場所で教育を行うのかということが確定しないと、NPOの申請、法律上必要な住所の登録、新しい学生の募集や先生の指導プランなど多くの支障が出てきます。ですので、ある程度お金を払っても、1年間を通じて場所が使えるというところを確保する必要が出てくるのです。 継承日本語教育で場所の確保が難しい理由として、1つは既存の学校設備を持った組織が継承日本語をやるということが少ないと言うことにあります。日本政府による日本人学校で教育設備を持っているというケース以外は、継承日本語の教室/学校を始めるには、週末あるいは放課後にだけ、どこかの他の学校や教育施設で場所を確保しなければなりません。既存の学校にコンタクトし、週末だけあるいは放課後だけスペースを借りるというのが、かなり大変で、かなりのお金を払っても長期間、週末だけキャンパスを貸し出してくれる学校や施設はそれほど多くありません。たまたま見つかっても、場所のレンタルの謝礼がネックになったり、突然、スペースが利用ができなくなったりするということもよくあるので、場所に翻弄されることは多いです。また、正式に教室や学校運営しようとすると、それぞれの地域の法律上、子供の安全や、教育設備等が法律によって決められていることもあり、そのような法律を準拠する設備がないので、結局利用できないということもあります。 最も良い場所は、当然、日系人がたくさん住んでいる居住地の近くがいいのですが、既存の継承日本語教室/学校との距離、電車やハイウェイなど通学手段の距離、謝礼の額など、多くの要素があり、なかなか上手く理想の場所に教室/学校が確保できるということは少ないようです。 カリキュラムと教材 カリキュラムに関しては、いろいろ違ったレベルでの課題があります。 ひとつは、インフォーマルな教室や学校では、教育関係の知識が持つ人がいないことがあるので、カリキュラムというコンセプトが無いと言うこともよくあります。 年間のスケジュールがあったり、いろんな行事やイベントの予定はあったりしても、クラスの中でどのような教育を行うのか、そしてその教育の効果をどのように評価するのかなど、カリキュラムの基本的なことが確立されていない事は、インフォーマルな集まりでは往々にあります。インフォーマルな集まりだと、長期的な計画等ができないという理由はあると思いますが、規模を大きくしたり、長期的に存続しようとするのであれば、カリキュラムは非常に大事になってきます。 カリキュラムのもう一つの問題としては、 日本の学習指導要領による教育と継承日本語のカリキュラムという二種類のカリキュラムがあることが挙げられます。 ...海外の日本語教育の現状 2021年度日本語教育機関調査 (概要)
 国際交流基金 (The Japan Foundation)が3年ごとにやっている全世界での日本語教育機関の調査アンケートの2021年の調査結果の概要が発表されています。コロナ禍の2021年で行われた調査であり、コロナの影響がどのようなものだったのかという事が注目されたアンケートでした。 1. The Japan Foundation (2022). 海外の日本語教育の現状 2021年度日本語教育機関調査より (Survey Report on Japanese-Language ...
国際交流基金 (The Japan Foundation)が3年ごとにやっている全世界での日本語教育機関の調査アンケートの2021年の調査結果の概要が発表されています。コロナ禍の2021年で行われた調査であり、コロナの影響がどのようなものだったのかという事が注目されたアンケートでした。 1. The Japan Foundation (2022). 海外の日本語教育の現状 2021年度日本語教育機関調査より (Survey Report on Japanese-Language ...「在外教育施設における教育の振興に関する法律」の公布・施行 (2022年6月27日)
 2022年6月27日に、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」が公布・施行されました。これにより、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設の日本政府の方針が大きく変わることになりました。大きな変更点は、これまでは日本人学校と補習授業校の運営に関しては、外務省及び文部科学省が主に所管をしていたのですが、今後は、総務省や経済産業省、国際交流基金、自治体国際化協会 (CLEAR)、日本貿易振興機構 (JETRO)、海外子女教育振興財団 (JOES)なども運営に積極的に参加するようになるそうです。 「在外教育施設における教育の振興に関する法律」の詳しい内容は、以下のページにあります。 2023年2月4日付の週刊NY生活誌にも詳しい変更の解説が書かれていました。 https://nyseikatsu.com/editions/899/899.pdf
2022年6月27日に、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」が公布・施行されました。これにより、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設の日本政府の方針が大きく変わることになりました。大きな変更点は、これまでは日本人学校と補習授業校の運営に関しては、外務省及び文部科学省が主に所管をしていたのですが、今後は、総務省や経済産業省、国際交流基金、自治体国際化協会 (CLEAR)、日本貿易振興機構 (JETRO)、海外子女教育振興財団 (JOES)なども運営に積極的に参加するようになるそうです。 「在外教育施設における教育の振興に関する法律」の詳しい内容は、以下のページにあります。 2023年2月4日付の週刊NY生活誌にも詳しい変更の解説が書かれていました。 https://nyseikatsu.com/editions/899/899.pdfCoalition of Community-Based Heritage Language Schools (CCBHLS連盟)の継承日本語学校メールリスト
 Coalition of Community-Based Heritage Language Schools (https://www.heritagelanguageschools.org)という全米で継承語を教えている学校や草の根プログラムのネットワーク化を目標にしている団体があるのですが、そこの日本語継承教室グループ (JHS)のメールリストができたということなんで案内しています。 2022年12月現在で、おおよそ50の団体がメールリストに参加しています。ほぼ全ての団体が継承日本語を草の根的に教えている団体で(日本人学校の補習校は、建前上、継承日本語は教えていないので参加してもらっていないそうです)、小さい団体をネットワーク化することでお互いにサポートや情報共有を図るようにしようという趣旨とのことです。 詳細は、以下の案内を参照ください。参加希望の方は、https://groups.google.com/g/jhs-ml/aboutまで。 JHS日本語継承教室グループ (Japanese Heritage Schools group by Coalition of ...
Coalition of Community-Based Heritage Language Schools (https://www.heritagelanguageschools.org)という全米で継承語を教えている学校や草の根プログラムのネットワーク化を目標にしている団体があるのですが、そこの日本語継承教室グループ (JHS)のメールリストができたということなんで案内しています。 2022年12月現在で、おおよそ50の団体がメールリストに参加しています。ほぼ全ての団体が継承日本語を草の根的に教えている団体で(日本人学校の補習校は、建前上、継承日本語は教えていないので参加してもらっていないそうです)、小さい団体をネットワーク化することでお互いにサポートや情報共有を図るようにしようという趣旨とのことです。 詳細は、以下の案内を参照ください。参加希望の方は、https://groups.google.com/g/jhs-ml/aboutまで。 JHS日本語継承教室グループ (Japanese Heritage Schools group by Coalition of ...Community-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 7-8, 2022)
 毎年ワシントンDCで行われているCommunity-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 7-8, 2022)ですが、今年は、オンラインと対面同時に行われるそうです。 対面での参加は、D.C.のAmerican Universityで行われ、その様子がオンライン参加の人のためにZoomでも公開されるようです。Keynote speakersには、バイリンガル教育で著名な、Ofelia García, Richard Brecht, Jim Cumminsなどが予定されているそうです。オンラインでの登録は$25、対面参加での登録は$75とのことです。
毎年ワシントンDCで行われているCommunity-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 7-8, 2022)ですが、今年は、オンラインと対面同時に行われるそうです。 対面での参加は、D.C.のAmerican Universityで行われ、その様子がオンライン参加の人のためにZoomでも公開されるようです。Keynote speakersには、バイリンガル教育で著名な、Ofelia García, Richard Brecht, Jim Cumminsなどが予定されているそうです。オンラインでの登録は$25、対面参加での登録は$75とのことです。全世界の日本の在外教育施設の在籍学生数 (2022年)
 海外教育振興財団(JOES)が発行する「海外子女教育」で数年に一回くらいの頻度で1月号に在外教育施設で学ぶ子女の在籍者数のレポートが掲載されています。今年(2022年)の1月号にも、「ただいま何人!?」という記事で、最新の在外教育施設で学ぶ子女の在籍者数が報告されていました。 海外子女教育振興財団 (2022). 「ただいま何人!?」在外教育施設在籍者数. 海外子女教育, 1, 44-49. https://www.joes.or.jp/cms/joes/pdf/publish/kikanshi2/202201omdt.pdf その記事によると、2022年の情報 (調査時期は2020年-2021年)では、全世界で日本政府が把握している「日本人学校」と「補習授業校」の在籍子女数は44,728人とのことです。また、その他にも、私立在外教育施設と区別される教育機関(「慶應義塾ニューヨーク学院」など)や文部科学省や外務省からの援助を受け取っていないが、日本語による教育を実施している教育施設(「ニューヨーク育英学園」など)に所属している子女が3,950人おり、合計で、48,678人の学生が全世界の在外教育施設で日本語を利用して勉強しています。 このブログポストにもありますが、在外にいるとされる日系子女の総数と比べてみると、この数はかなり低い数になっています。おそらく理由としては、以下のようなものが挙げられると考えられます。 日本政府が把握している在外教育施設に含まれない教育機関(草の根的な小さな週末学校など)で勉強する子女が調査に含まれていない。 現地校のみで、日本語の学習などは家庭で行なっている。あるいは、日本語による学習は全く行っていない。 実際に調査に含まれていない子女がどれくらいいるのか、どのくらいの日系子女が日本語による学校教育をおこなっていないのかは、今のところわかっていません。 他方、わかっている情報を見てみると、いろいろな興味深いパターンが見えてきます。「海外子女教育」の2019年号でも同様な情報が公開されたのですが、その際の合計子女数は59,795人とのことでした。2022年の同じ調査の数が、48,678ということですので、ここ3年で急激に在外教育施設で学ぶ子女の数は減っています。これが、コロナ禍の中で行われた調査であったため、一時的に学生数が減っているのか、長期的な傾向として減っているのかはわかりません。この記事では、最も子女が多かった時期 (2013年前後)では、70,000人近い子女が在外教育施設で学んでいたということですので、もしかしたら長期的な傾向として減少している中で、コロナ禍のために多くの学校が閉鎖や中止に追い込まれている可能性は大いにあると思われます。 2022年のデータを見てみると、学齢期前(幼稚部)が4,285人、小学生が32,991人、中学生が8,995人、高校生が2,407人とのことですので、これまで通り、多くの子女は小学生の年齢で、中学生や高校生のレベルで日本語での教育を続ける子女はごく一部のようです。 地域的には、アジア 14,117人 (29.0%)、北米 19,409人 (39.9%)、欧州 10,444人 (21.5%)が主な地域になっています。 他方、地域ごとに利用する教育機関の種類は大きく異なり、大まかには、アジア圏では全日制の日本人学校を選択する子女が多いのですが、北米および欧州では、週末のみの補習授業校を選択する子女が多数を占めています。これは、平日に通う現地校が、言語、政治、宗教の違いなどから選択しづらい地域がアジアには多く、他方、北米と欧州では、現地校に通っても日本人学校に近い基準の教育を受けられることが多いためだと思われます。 日本人学校に通う子女だけのデータと補習授業校通う子女だけのデータを地域別に分けてみると、その傾向がよくわかります(上記の全体のチャートを比べてみてください)。大まかに言うと、日本人学校というと、その大多数(76.3%)がアジアに存在し、そのため、アジア圏で補習授業校に通っている子女はごく僅かになります。他方、補習授業校というと、多くが北米 ...
海外教育振興財団(JOES)が発行する「海外子女教育」で数年に一回くらいの頻度で1月号に在外教育施設で学ぶ子女の在籍者数のレポートが掲載されています。今年(2022年)の1月号にも、「ただいま何人!?」という記事で、最新の在外教育施設で学ぶ子女の在籍者数が報告されていました。 海外子女教育振興財団 (2022). 「ただいま何人!?」在外教育施設在籍者数. 海外子女教育, 1, 44-49. https://www.joes.or.jp/cms/joes/pdf/publish/kikanshi2/202201omdt.pdf その記事によると、2022年の情報 (調査時期は2020年-2021年)では、全世界で日本政府が把握している「日本人学校」と「補習授業校」の在籍子女数は44,728人とのことです。また、その他にも、私立在外教育施設と区別される教育機関(「慶應義塾ニューヨーク学院」など)や文部科学省や外務省からの援助を受け取っていないが、日本語による教育を実施している教育施設(「ニューヨーク育英学園」など)に所属している子女が3,950人おり、合計で、48,678人の学生が全世界の在外教育施設で日本語を利用して勉強しています。 このブログポストにもありますが、在外にいるとされる日系子女の総数と比べてみると、この数はかなり低い数になっています。おそらく理由としては、以下のようなものが挙げられると考えられます。 日本政府が把握している在外教育施設に含まれない教育機関(草の根的な小さな週末学校など)で勉強する子女が調査に含まれていない。 現地校のみで、日本語の学習などは家庭で行なっている。あるいは、日本語による学習は全く行っていない。 実際に調査に含まれていない子女がどれくらいいるのか、どのくらいの日系子女が日本語による学校教育をおこなっていないのかは、今のところわかっていません。 他方、わかっている情報を見てみると、いろいろな興味深いパターンが見えてきます。「海外子女教育」の2019年号でも同様な情報が公開されたのですが、その際の合計子女数は59,795人とのことでした。2022年の同じ調査の数が、48,678ということですので、ここ3年で急激に在外教育施設で学ぶ子女の数は減っています。これが、コロナ禍の中で行われた調査であったため、一時的に学生数が減っているのか、長期的な傾向として減っているのかはわかりません。この記事では、最も子女が多かった時期 (2013年前後)では、70,000人近い子女が在外教育施設で学んでいたということですので、もしかしたら長期的な傾向として減少している中で、コロナ禍のために多くの学校が閉鎖や中止に追い込まれている可能性は大いにあると思われます。 2022年のデータを見てみると、学齢期前(幼稚部)が4,285人、小学生が32,991人、中学生が8,995人、高校生が2,407人とのことですので、これまで通り、多くの子女は小学生の年齢で、中学生や高校生のレベルで日本語での教育を続ける子女はごく一部のようです。 地域的には、アジア 14,117人 (29.0%)、北米 19,409人 (39.9%)、欧州 10,444人 (21.5%)が主な地域になっています。 他方、地域ごとに利用する教育機関の種類は大きく異なり、大まかには、アジア圏では全日制の日本人学校を選択する子女が多いのですが、北米および欧州では、週末のみの補習授業校を選択する子女が多数を占めています。これは、平日に通う現地校が、言語、政治、宗教の違いなどから選択しづらい地域がアジアには多く、他方、北米と欧州では、現地校に通っても日本人学校に近い基準の教育を受けられることが多いためだと思われます。 日本人学校に通う子女だけのデータと補習授業校通う子女だけのデータを地域別に分けてみると、その傾向がよくわかります(上記の全体のチャートを比べてみてください)。大まかに言うと、日本人学校というと、その大多数(76.3%)がアジアに存在し、そのため、アジア圏で補習授業校に通っている子女はごく僅かになります。他方、補習授業校というと、多くが北米 ...国際交流基金による日本語デジタルライブラリー
 アメリカの国際交流基金が日本の書籍のデジタルライブラリーの提供を開始するとのことです。カナダのトロントにある国際交流基金では、かなり以前から同様なサービスが開始されているそうで、そちらで提供されている書籍はhttps://jf.overdrive.comで見られるようになっています。 アメリカでの日本語デジタルライブラリーサービスが、カナダのものと同様な蔵書になるかはわからないのですが、カナダでのサービスを見ると「鬼滅の刃」やSpyxFamilyなどの英語版の漫画ebookや、日本語学習書籍 (交流基金の「まるごと」シリーズ、「げんき」、その他の日本語学習の参考文献など)、文庫本など、とても豊富な蔵書になっています。 2022年6月2日(木)現在、アメリカでの日本語デジタルライブラリーサービスのアカウントを希望する方の情報を以下のリンクで集めているとのことですので、興味がある方は以下のリンクを参照ください。 ------------------------------ In collaboration with our New York and Toronto offices, The Japan Foundation Los Angeles ...
アメリカの国際交流基金が日本の書籍のデジタルライブラリーの提供を開始するとのことです。カナダのトロントにある国際交流基金では、かなり以前から同様なサービスが開始されているそうで、そちらで提供されている書籍はhttps://jf.overdrive.comで見られるようになっています。 アメリカでの日本語デジタルライブラリーサービスが、カナダのものと同様な蔵書になるかはわからないのですが、カナダでのサービスを見ると「鬼滅の刃」やSpyxFamilyなどの英語版の漫画ebookや、日本語学習書籍 (交流基金の「まるごと」シリーズ、「げんき」、その他の日本語学習の参考文献など)、文庫本など、とても豊富な蔵書になっています。 2022年6月2日(木)現在、アメリカでの日本語デジタルライブラリーサービスのアカウントを希望する方の情報を以下のリンクで集めているとのことですので、興味がある方は以下のリンクを参照ください。 ------------------------------ In collaboration with our New York and Toronto offices, The Japan Foundation Los Angeles ...アリゾナ州での小規模な継承日本語学校の設立に関する調査
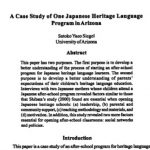 Siegel, Y. S. (2004). A Case Study of One Japanese Heritage Language Program in Arizona. ...
Siegel, Y. S. (2004). A Case Study of One Japanese Heritage Language Program in Arizona. ...