継承語に関する研究について紹介しています。日本語に特化した研究以外にも、他の言語の研究なども紹介し、総合的に継承語の維持について考えています。他にも、継承語の研究に関する入門書なども紹介しています。
HLXChange.com: 継承語教育 (日本語を含む言語全般の)サポートページ
 UCLAのNational Heritage Language Resource Center (NHLRC)のダイレクターをやっておられるCal State Long BeachのMaria Carreira先生やその同僚の方が、継承語教育(言語を問わず、全ての言語の継承語教育)のサポートをするためにHLXChange.com (https://www.hlxchange.com)というウェブサイトを公開されたそうです。 まだ色々開発中のようですが、すでにいくつかの継承語教育に関するリソースが紹介されています。このページでは、いくつかの短いYouTube videosでJames Lang/Flower DarbyによるSmall Teachingという手法が紹介されています。
UCLAのNational Heritage Language Resource Center (NHLRC)のダイレクターをやっておられるCal State Long BeachのMaria Carreira先生やその同僚の方が、継承語教育(言語を問わず、全ての言語の継承語教育)のサポートをするためにHLXChange.com (https://www.hlxchange.com)というウェブサイトを公開されたそうです。 まだ色々開発中のようですが、すでにいくつかの継承語教育に関するリソースが紹介されています。このページでは、いくつかの短いYouTube videosでJames Lang/Flower DarbyによるSmall Teachingという手法が紹介されています。ロサンゼルス近郊の継承日本語話者の人口動勢 (Treist et al., 2022)
 Mutilingual La La Landというロサンゼルス近郊の継承語話者の人口動勢の本が2022年に出版されるのですが、その中の一章で、継承日本語の最近の人口動勢について書かれています。 Triest, M. A., Hayashi Takakura, A., & Hitchins Chik, C. (2022). Japanese: ...
Mutilingual La La Landというロサンゼルス近郊の継承語話者の人口動勢の本が2022年に出版されるのですが、その中の一章で、継承日本語の最近の人口動勢について書かれています。 Triest, M. A., Hayashi Takakura, A., & Hitchins Chik, C. (2022). Japanese: ...International Guidelines for Professional Practices in Community-Based Heritage Language Schools
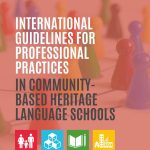 Coalition of Community-Based Heritage Language SchoolsというUCLAにある継承語教育の研究団体が、全世界のコミュニティーベース学校(正規の学校ではなく、保護者やコミュニティー主体で始まる継承語の保持を目標とした週末やアフタースクールの学校)を調査し、(1) 継承語学校に当てはまる共通の教育原理とは何か、また、(2)継承語学校が指針として参考にできる質の高い教育とは何かを定義したガイドラインが作成されました。 Aberdeen, T., Cannizzaro, G., Douglas, M. O., Emilsson Peskova, ...
Coalition of Community-Based Heritage Language SchoolsというUCLAにある継承語教育の研究団体が、全世界のコミュニティーベース学校(正規の学校ではなく、保護者やコミュニティー主体で始まる継承語の保持を目標とした週末やアフタースクールの学校)を調査し、(1) 継承語学校に当てはまる共通の教育原理とは何か、また、(2)継承語学校が指針として参考にできる質の高い教育とは何かを定義したガイドラインが作成されました。 Aberdeen, T., Cannizzaro, G., Douglas, M. O., Emilsson Peskova, ...Community-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 8-9, 2021)
 毎年ワシントンDCで行われているCommunity-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 8-9, 2021)ですが、今年もオンラインで行われ、その際の発表の一部の録画が一般に公開されています。 いろいろな発表があるのですが、特に良いと思ったのは、継承語教育をサポートしている全米の団体の短い紹介ビデオがありました。継承語教育の運営者や保護者の方にはあまり直接知る機会がない団体ですが、さまざまなサポートをしているようなので、みても良いかと思います。紹介されていた団体は、以下の団体です。 ACTFL, America's Languages Initiative, Center for Applied Linguistics ...
毎年ワシントンDCで行われているCommunity-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 8-9, 2021)ですが、今年もオンラインで行われ、その際の発表の一部の録画が一般に公開されています。 いろいろな発表があるのですが、特に良いと思ったのは、継承語教育をサポートしている全米の団体の短い紹介ビデオがありました。継承語教育の運営者や保護者の方にはあまり直接知る機会がない団体ですが、さまざまなサポートをしているようなので、みても良いかと思います。紹介されていた団体は、以下の団体です。 ACTFL, America's Languages Initiative, Center for Applied Linguistics ...海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査
 もう去年の話で少し出遅れているのですが、国際交流基金 (The Japan Foundation)が3年ごとにやっている全世界での日本語教育機関の調査アンケートの2018年の調査結果がレポートとして発表されました。 The Japan Foundation. (2020). 海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査より (Survey Report on Japanese-Language Education Abroad ...
もう去年の話で少し出遅れているのですが、国際交流基金 (The Japan Foundation)が3年ごとにやっている全世界での日本語教育機関の調査アンケートの2018年の調査結果がレポートとして発表されました。 The Japan Foundation. (2020). 海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査より (Survey Report on Japanese-Language Education Abroad ...「おひさま」プロジェクト
 継承語話者向けの教科書「おひさま」の著者の方々(山本絵美・上野淳子・米良好恵)が2021年から教科書だけでなく、「おひさま」プロジェクトとして、定期的な公演、ワークショップなどの活動を行っているそうです。日本語を継承語として話す子供たちに関する教育情報や、おすすめの本などがウェブサイトで見られるようになっています。 月1,500円で会員登録もでき、子供の年齢に合わせた教材の配布や、各種講演会情報、教育情報を掘り下げたコラムなどを配布してくれるそうです。 現在、ウェブサイトと「おひさま」のYouTube channelでは、無料で講演会の様子が見られるようになっています。
継承語話者向けの教科書「おひさま」の著者の方々(山本絵美・上野淳子・米良好恵)が2021年から教科書だけでなく、「おひさま」プロジェクトとして、定期的な公演、ワークショップなどの活動を行っているそうです。日本語を継承語として話す子供たちに関する教育情報や、おすすめの本などがウェブサイトで見られるようになっています。 月1,500円で会員登録もでき、子供の年齢に合わせた教材の配布や、各種講演会情報、教育情報を掘り下げたコラムなどを配布してくれるそうです。 現在、ウェブサイトと「おひさま」のYouTube channelでは、無料で講演会の様子が見られるようになっています。アメリカ経済での日本語・英語のバイリンガル能力の必要性
 American Council on the Teaching of Foreign Languages (2019). Making Languages Our Business: Addressing Foreign ...
American Council on the Teaching of Foreign Languages (2019). Making Languages Our Business: Addressing Foreign ...継承日本語話者の話す日本語の言語学的特徴
 Nishikawa, T. (2019). 継承語の言語的特徴. In Kondo-Brown, Kimi, Sakamoto, Mitsuyo, & Nishikawa, Tomomi (Eds.), 親と子をつなぐ継承語教育: 日本・外国にルーツを持つ子供. ...
Nishikawa, T. (2019). 継承語の言語的特徴. In Kondo-Brown, Kimi, Sakamoto, Mitsuyo, & Nishikawa, Tomomi (Eds.), 親と子をつなぐ継承語教育: 日本・外国にルーツを持つ子供. ...継承日本語話者の日本語能力をどう測定するか
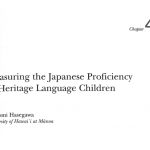 Hasegawa, T. (2008). Measuring the Japanese proficiency of heritage language children. In K. Kondo-Brown ...
Hasegawa, T. (2008). Measuring the Japanese proficiency of heritage language children. In K. Kondo-Brown ...アメリカの日本語教育(継承語以外の日本語教育も含む)についてのアーティクル
 Kondo-Brown, K. (2014). Japanese in the United States. (23). In T. G. Wiley, J. K. ...
Kondo-Brown, K. (2014). Japanese in the United States. (23). In T. G. Wiley, J. K. ...