継承語に関する研究について紹介しています。日本語に特化した研究以外にも、他の言語の研究なども紹介し、総合的に継承語の維持について考えています。他にも、継承語の研究に関する入門書なども紹介しています。
1980年のアメリカの日本語継承語学校 (from Fishman (1980))
 アメリカの継承語教育の歴史を調べていて、おそらくアメリカの継承語学校の一番古い継承語学校の全米のリサーチであろうと思われるFishman (1964, 1980)を読みました。日本の継承語学校のことについても書かれていたので紹介しています。 Fishman, J. A. & Nahirny, V. C. (1964). The ...
アメリカの継承語教育の歴史を調べていて、おそらくアメリカの継承語学校の一番古い継承語学校の全米のリサーチであろうと思われるFishman (1964, 1980)を読みました。日本の継承語学校のことについても書かれていたので紹介しています。 Fishman, J. A. & Nahirny, V. C. (1964). The ...2005年から2023年のニューヨーク市の日本語話者数の変遷
 ニューヨーク市の最近の英語以外の言語の変遷を調べる機会があり、その中に日本語のデータもあったので、それをまとめてみました。今回利用したのは、U.S. Census Bureauが毎年行っているAmerican Community Surveys (ACS)のデータです。ACSは、10年事に行われるcensus (国勢調査)とは別に、毎年、数%のサンプルとして抽出された人だけが返答する調査で、2005年より行われました。 Stevens (1999)で詳しく述べられていますが、アメリカの長期的な言語変遷を調べるのは容易ではありません。大きな理由としては、国勢調査で言語に関する質問が少ない、あるいはなかった期間が多く、また、言語の質問も何十年か毎に変更されていくので、継承語のように世代をまたぐ変遷を通時的に調べるのが難しいです。また、長い間、"race" (民族)に関する質問と"Mother Tongue"に関する質問は相関性があると考えられていたり (例えば、ドイツからの移民と回答したら、「ドイツ語」が母語であるのような感じ)、"Mother Tongue" (母語)という定義が曖昧な用語で言語に関する質問が聞かれていたり、回答の選択肢が5-6種類の言語に限られていて、他の言語は全て"other"に分類されたりと、かなりの予想と憶測を使わないと利用できないような言語データになっています。 1980年から、ようやく、言語に関する質問が標準化されてきて、以下のような3ステップの質問になりました。 ...
ニューヨーク市の最近の英語以外の言語の変遷を調べる機会があり、その中に日本語のデータもあったので、それをまとめてみました。今回利用したのは、U.S. Census Bureauが毎年行っているAmerican Community Surveys (ACS)のデータです。ACSは、10年事に行われるcensus (国勢調査)とは別に、毎年、数%のサンプルとして抽出された人だけが返答する調査で、2005年より行われました。 Stevens (1999)で詳しく述べられていますが、アメリカの長期的な言語変遷を調べるのは容易ではありません。大きな理由としては、国勢調査で言語に関する質問が少ない、あるいはなかった期間が多く、また、言語の質問も何十年か毎に変更されていくので、継承語のように世代をまたぐ変遷を通時的に調べるのが難しいです。また、長い間、"race" (民族)に関する質問と"Mother Tongue"に関する質問は相関性があると考えられていたり (例えば、ドイツからの移民と回答したら、「ドイツ語」が母語であるのような感じ)、"Mother Tongue" (母語)という定義が曖昧な用語で言語に関する質問が聞かれていたり、回答の選択肢が5-6種類の言語に限られていて、他の言語は全て"other"に分類されたりと、かなりの予想と憶測を使わないと利用できないような言語データになっています。 1980年から、ようやく、言語に関する質問が標準化されてきて、以下のような3ステップの質問になりました。 ...継承日本語話者の日本語能力の優位性に関する研究
 Kondo-Brown, K. (2005). Differences in language skills: Heritage Language Learner Sub-groups ...
Kondo-Brown, K. (2005). Differences in language skills: Heritage Language Learner Sub-groups ...1980年代のニューヨークでの継承日本語教育に関する記事
 1980年代の継承日本語教育についての記事をThe New York Timesで見つけました。二つ記事があり、一つは、全日の日本人学校についての記事、もう一つは、土曜日の補習校についての記事です。日本の高度成長期の最盛期で、経済分野で日本のプレゼンスが多くなり、ニューヨークの一般社会でも日本人コミュニティーについての興味が多かったことを伺わせます。 今、北米には4校の全日制日本人学校がありますが、そのうち2校はニューヨーク周辺にあります(ニュージャージ日本人学校とニューヨーク日本人学校)。これらの学校は、もともと1970年頃から増加してきた日本からの一時駐在家庭の子どもたちの教育のために設立された経緯があります。現在、ニューヨーク日本人学校はコネチカット州のリバーデールにありますが、設立当初はニューヨーク市内にあり、1980年代にはクイーンズにも全日制日本人学校が存在していました。また、それとは別に、現地校に通う日系の子どもたちのための補習校がニューヨーク各地にあったそうです(記事によれば12校もあったとのことです)。 記事の内容から、日本人学校に通う子どもたちも補習校に通う子どもたちも、最終的には日本に帰国するという考え方が確立していたようで、1980年代には「帰国組」と「永住組」というような区分はあまりなかったようです(あるいは、新聞記事など公式な場では「永住組」の子どもたちが話題に上ることはなかったようです)。 2000年以降は、北米の補習校に関して永住予定の子どもたちが増え、帰国後に日本の教育システムについていくことを目的としない保護者が大半を占めるようになりました。補習校は、日本の言語や文化をできるだけ保持することを目的としているという現在一般的に受け入れられている考え方とはかなり異なる雰囲気があったことが伺えます。
1980年代の継承日本語教育についての記事をThe New York Timesで見つけました。二つ記事があり、一つは、全日の日本人学校についての記事、もう一つは、土曜日の補習校についての記事です。日本の高度成長期の最盛期で、経済分野で日本のプレゼンスが多くなり、ニューヨークの一般社会でも日本人コミュニティーについての興味が多かったことを伺わせます。 今、北米には4校の全日制日本人学校がありますが、そのうち2校はニューヨーク周辺にあります(ニュージャージ日本人学校とニューヨーク日本人学校)。これらの学校は、もともと1970年頃から増加してきた日本からの一時駐在家庭の子どもたちの教育のために設立された経緯があります。現在、ニューヨーク日本人学校はコネチカット州のリバーデールにありますが、設立当初はニューヨーク市内にあり、1980年代にはクイーンズにも全日制日本人学校が存在していました。また、それとは別に、現地校に通う日系の子どもたちのための補習校がニューヨーク各地にあったそうです(記事によれば12校もあったとのことです)。 記事の内容から、日本人学校に通う子どもたちも補習校に通う子どもたちも、最終的には日本に帰国するという考え方が確立していたようで、1980年代には「帰国組」と「永住組」というような区分はあまりなかったようです(あるいは、新聞記事など公式な場では「永住組」の子どもたちが話題に上ることはなかったようです)。 2000年以降は、北米の補習校に関して永住予定の子どもたちが増え、帰国後に日本の教育システムについていくことを目的としない保護者が大半を占めるようになりました。補習校は、日本の言語や文化をできるだけ保持することを目的としているという現在一般的に受け入れられている考え方とはかなり異なる雰囲気があったことが伺えます。全世界の日本の在外教育施設の在籍学生数 (2025年)
 毎年、海外教育振興財団(JOES)が発表している在外教育施設で学ぶ子女の在籍者数の2025年のレポートが発表されています。 ただいま何人!? (在外教育施設在籍者数). 2025年1月. https://joes-magazine.com/articles/1435 2024年のレポートでは、日本人学校の児童数が16,958人 (幼児部、小学部、中学部、高等部; その他は除く)で、補習授業校の児童数が29,924人だったのですが、2025年には、それぞれ、日本人学校が17,458人、補習授業校が31,057人と増加の傾向が引き続き続いています。 2020年以降に、コロナ禍で全世界で在外教育在籍者数が減ったのですが、2020年の頃にはまだ及ばないですが、着実に在外教育在籍者数は増えている状況です。地域別には、アフリカ、中南米、太洋州、中東など、もともと在外教育在籍者数が少なかった地域では、2019年レベルに戻っています。特に、大洋州は、コロナ禍の前を超える子女が在外教育施設で勉強しており、ゆっくりとした回復を見せている北米、欧州、アジアとは違ったパターンを見せています。 以前も書きましたが、北米と欧州での在外教育施設は、そのほとんどが補習校で、アジアでは、ほとんどが全日の日本人学校です。そのパターンは2025年のデータでも変わっていません。日本人学校、補習授業校だけを比べると、北米では、98% (16,767人)の子女が補習授業校に通学しており、全日の日本人学校に通うのはわずか2% (339人)です。他方で、アジアで、補習授業校に通学するのは10%程度 (1,574人)で、9割の子女 (13,694人) は全日の日本人学校に通学しています。 北米だけのデータを見てみると、以下のようなパターンが見られます。 ...
毎年、海外教育振興財団(JOES)が発表している在外教育施設で学ぶ子女の在籍者数の2025年のレポートが発表されています。 ただいま何人!? (在外教育施設在籍者数). 2025年1月. https://joes-magazine.com/articles/1435 2024年のレポートでは、日本人学校の児童数が16,958人 (幼児部、小学部、中学部、高等部; その他は除く)で、補習授業校の児童数が29,924人だったのですが、2025年には、それぞれ、日本人学校が17,458人、補習授業校が31,057人と増加の傾向が引き続き続いています。 2020年以降に、コロナ禍で全世界で在外教育在籍者数が減ったのですが、2020年の頃にはまだ及ばないですが、着実に在外教育在籍者数は増えている状況です。地域別には、アフリカ、中南米、太洋州、中東など、もともと在外教育在籍者数が少なかった地域では、2019年レベルに戻っています。特に、大洋州は、コロナ禍の前を超える子女が在外教育施設で勉強しており、ゆっくりとした回復を見せている北米、欧州、アジアとは違ったパターンを見せています。 以前も書きましたが、北米と欧州での在外教育施設は、そのほとんどが補習校で、アジアでは、ほとんどが全日の日本人学校です。そのパターンは2025年のデータでも変わっていません。日本人学校、補習授業校だけを比べると、北米では、98% (16,767人)の子女が補習授業校に通学しており、全日の日本人学校に通うのはわずか2% (339人)です。他方で、アジアで、補習授業校に通学するのは10%程度 (1,574人)で、9割の子女 (13,694人) は全日の日本人学校に通学しています。 北米だけのデータを見てみると、以下のようなパターンが見られます。 ...補習校・継承語学校がない場所での継承日本語の保持
 Hashimoto, K. & Lee, J. S. (2011). Heritage-Language Literacy Practices: A ...
Hashimoto, K. & Lee, J. S. (2011). Heritage-Language Literacy Practices: A ...継承語学習者のためのアンケートテンプレート: Q-Bex
 De Cat, C., Kašćelan, D., Prévost, P., Serratrice, L., Tuller, L., ...
De Cat, C., Kašćelan, D., Prévost, P., Serratrice, L., Tuller, L., ...北米での東アジア言語(中国語、韓国語、日本語)の継承語学校
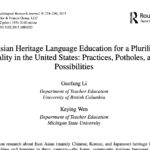 Li, G., & Wen, K. (2015). East Asian heritage language education ...
Li, G., & Wen, K. (2015). East Asian heritage language education ...日本の教科書のデジタル化 (文部科学省のデジタル教科書推進ワーキンググループ)
 文部科学省のデジタル教科書推進ワーキンググループが、日本でのデジタル教科書の利用に関しての審議のまとめの素案が発表されました。 これまでも英語などの一部の科目では試験的にデジタル教科書が使われてきたのですが、今回の審議のまとめでは、教科書の形態として「紙だけでなくデジタルも教科書と認める」方向と、大きくデジタル化へと舵きりが行われるようです。導入時期は、2030年ごろとかなり先の話ですが、教科書の検定も、紙媒体のものとデジタあるのものの両方を開始するということで、これにより教科書のデジタル化がかなり進むのだと思います。 デジタル教科書の議論の中では、紙媒体ではない教材への懸念が大きく議論されていますが、他方で、デジタルだからこそできることについても多く紹介されてきました。継承日本語学校では、日本の教科書は難しすぎて使えないケースが多いのですが、デジタル教科書では、教科書利用のネックになっている漢字へのルビ表示や、分かち書きなどができ、文化的にわかりづらいと思われる事柄についても、QRコードなどがついていて、その文化背景を紹介するようなこともできます。デジタルですと、配送などの問題も解決しますし、継承語教育での教科書の利用も糸口が見えてきたのかと感じます。 実際に、海外の配布教科書になっている光村図書の国語教科書のデジタル版(指導用)の紹介がここにありました。 https://www.youtube.com/watch?v=U68zZHV8Wdk 今年の時点で既に公開されているデジタル教科書(指導用)では、テキストの配色や文字の大きさ・行間の調整、本文の読み上げ、総ルビ・分かち書き表示などができるそうです。
文部科学省のデジタル教科書推進ワーキンググループが、日本でのデジタル教科書の利用に関しての審議のまとめの素案が発表されました。 これまでも英語などの一部の科目では試験的にデジタル教科書が使われてきたのですが、今回の審議のまとめでは、教科書の形態として「紙だけでなくデジタルも教科書と認める」方向と、大きくデジタル化へと舵きりが行われるようです。導入時期は、2030年ごろとかなり先の話ですが、教科書の検定も、紙媒体のものとデジタあるのものの両方を開始するということで、これにより教科書のデジタル化がかなり進むのだと思います。 デジタル教科書の議論の中では、紙媒体ではない教材への懸念が大きく議論されていますが、他方で、デジタルだからこそできることについても多く紹介されてきました。継承日本語学校では、日本の教科書は難しすぎて使えないケースが多いのですが、デジタル教科書では、教科書利用のネックになっている漢字へのルビ表示や、分かち書きなどができ、文化的にわかりづらいと思われる事柄についても、QRコードなどがついていて、その文化背景を紹介するようなこともできます。デジタルですと、配送などの問題も解決しますし、継承語教育での教科書の利用も糸口が見えてきたのかと感じます。 実際に、海外の配布教科書になっている光村図書の国語教科書のデジタル版(指導用)の紹介がここにありました。 https://www.youtube.com/watch?v=U68zZHV8Wdk 今年の時点で既に公開されているデジタル教科書(指導用)では、テキストの配色や文字の大きさ・行間の調整、本文の読み上げ、総ルビ・分かち書き表示などができるそうです。継承日本語話者の日本語ボキャブラリーに影響を与える要素
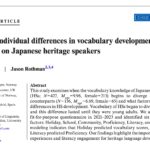 Kubota, M. & Rothman, J. (2024). Modeling individual differences in vocabulary ...
Kubota, M. & Rothman, J. (2024). Modeling individual differences in vocabulary ...