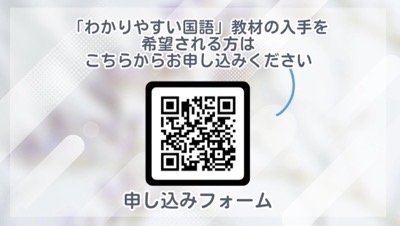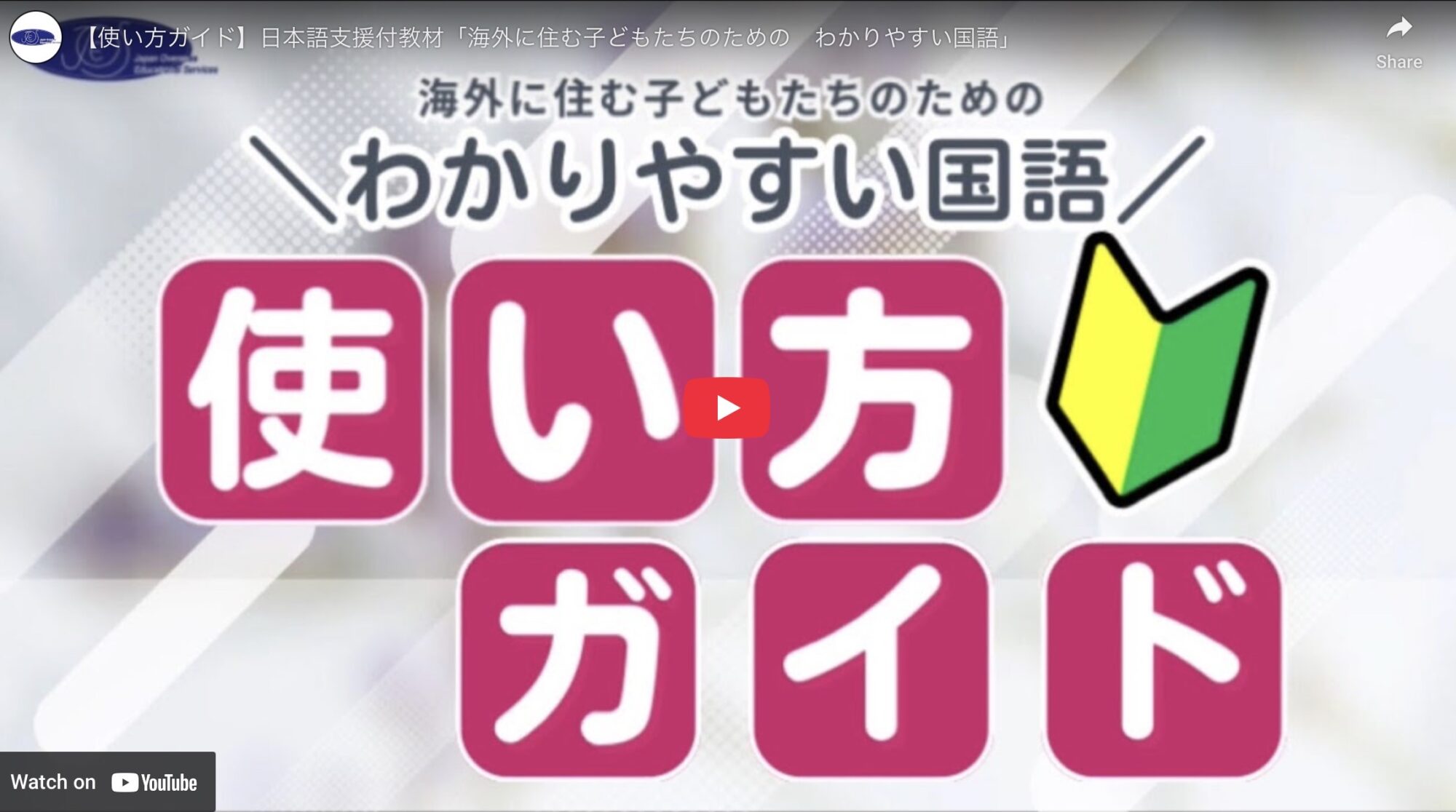在外で日本語を学習する子女のための出国前、帰国後のサポートや、海外での教科書の配布などを行なっている「海外子女教育振興財団 (JOES)」が、「海外に住む子どもたちのためのわかりやすい国語」という海外で日本語を継承語として学習する子女の支援を行うプロジェクトを開始しました。
元々、「海外子女教育振興財団 (JOES)」は、文部科学省の許可を受けた財団法人として、文科省の指針に沿って、1970年代から海外で日本語で教育を受ける子女の支援をしてきた組織です。これまでは、1970年代の日本の高度成長期の際に海外赴任していた、いわゆる「駐在組」のみへの支援をしてきたのですが、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」の制定などもあり、いわゆる「永住組」の継承語支援にも2024年から乗り出した経緯があります。
正式にJOESの方針がどのように変わったのかは発表されていないので、個人的な意見になりますが、自分が感じるJOESの方針で変わった点、変わっていない点は以下の通りです。
- これまでは、JOESのサービスの対象は、いずれ日本に帰国する予定のある「長期滞在者」の子女の支援であり、目標としては、それらの子女が日本に帰国した際に、日本の学校でも問題なく学習を続けていける事だった。それが、今回は、帰国の前提がない「永住者」を視野にいれたサービスも開始されるようになった。
- これまでは、JOESによる海外での日本語による教育は、全日の「日本人学校」と週末の「補習授業校」の2つが主な柱だったが、それに「継承日本語教室」やオンラインによるホームスクールなども視野に入った。
- 文部科学省の方針に沿ってサービスを提供しているので、JOESの対象はあくまで、日本国籍を持った日本人子女のみ。「永住組」の子女全員がJOESの対象になったわけでなく、日本国籍を有している子女だけが対象。対象の設定は、日本語を継承語として学ぶ意思などではなく、あくまで国籍と法律による国の責務による。ただ、逆に言うと、日本国籍を持っていれば、日本語能力が完全に消失した子女も対象になっている(日本語を外国語として学ぶサポートも入る)。
- 日本の検定教科書を使用した日本語教育は譲れない様子。これは、継承語として日本語を学ぶ子女の第一の理由が、「日本の教科書での指導だとわからない」という事実を考えると、矛盾を含む方針だと思う。
で、今回、発表された「海外に住む子どもたちのための わかりやすい国語」プロジェクトですが、大まかな概要としては以下の通りです。
- プロジェクトの対象は、国語のみ。
- プロジェクトの大きな柱は、日本の教科書を使った継承語話者向けへの年間カリキュラムの公開。日本語の教科書は使うけれども、「学習指導要領」ではない、カリキュラムを作る。具体的には、指導量は「学習指導要領」のおおよそ60%くらい、漢字の特別な支援、日本文化や伝統行事などの楽しさを強調するとのこと。
- 新しく作られたカリキュラムにそった、単元毎の指導ガイド(学習活動計画案)も作成。ワークシートでは、分かち書きやふりがな、イラストや写真の活用した読み方の支援、ブレインストームや穴埋めを利用した書き方の支援など継承語教育指導を考慮したワークシートになっている。
- 日本に住んだことがない継承語話者も考慮した日本の伝統行事、四季などを特に丁寧に解説。
- これまでは、読み書きの一部として指導されていた「漢字」の指導は、別目標として独立してしどうする。漢字の成り立ちや、部首の意味解説などを詳しく説明して、継承語話者の大きな課題である漢字の学習を特に注力して支援する。
この「海外に住む子どもたちのための わかりやすい国語」のカリキュラムと教材に興味がある方は、上記の紹介ビデオの最後に教材入手のためのフォームへのQRコードが提示されていますので、そこからリクエストできるそうです。カリキュラムと教材は無料で提供されているとのことです。