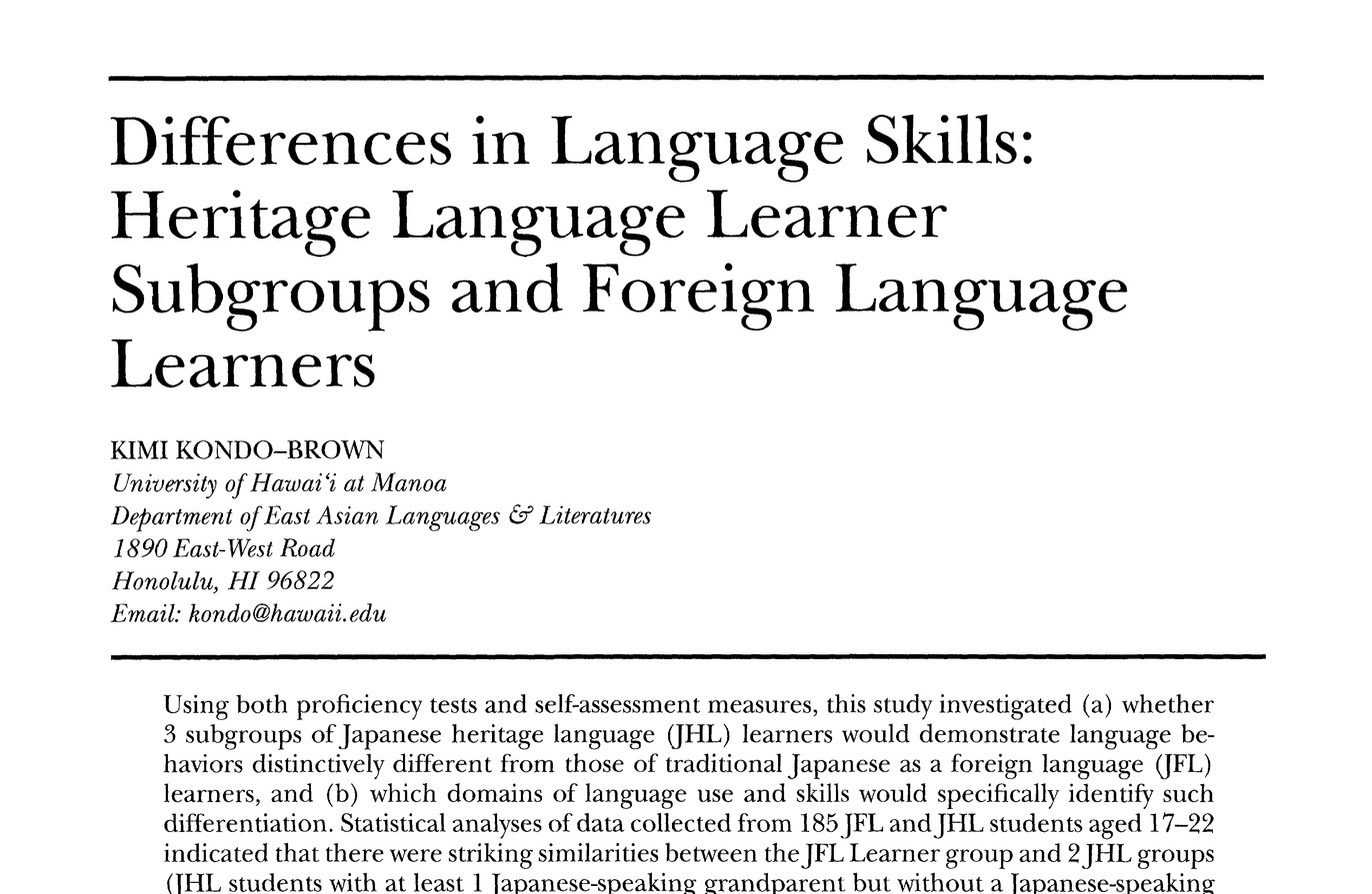- Kondo-Brown, K. (2005). Differences in language skills: Heritage Language Learner Sub-groups and Foreign Language Learners. The Modern Language Journal, 89, 563-581.
こちらでも紹介している継承日本語語教育についての本などの著書がある近藤ブラウン先生の初期のころの研究論文です。継承日本語話者が、第二言語学習者よりも発音、頻度の高い文法や語彙などの言語能力の一部の能力で優位だけれども、漢字や頻度が低い文法や語彙などの他の言語分野では第二言語学習者と比べても優位ではないのではないかという研究がたくさんあるのですが、それに類似したトピックで、継承日本語話者というひとくくりにされているグループの中で、言語学的な優位性があるのはどのグループかということについて研究されています。
継承日本語のグループとしては、(1) Descent/Identity Group (日系アメリカ人としてアメリカで生まれ家庭で日本語を話す人がいない子女)、(2) Grandparent Group (日系アメリカ人としてアメリカで生まれ、祖父母のいずれかが日本語を話す子女)、(3) Parent Group (日本あるいはアメリカで生まれ、アメリカで育った、両親のいずれかが日本語を話す子女)、(4) Learner Group (日系ではないけれども日本語を第二言語として学習した子女)の4グループです。
調査に使われたのは、ハワイ大学で使われている日本語のプレースメントテストの改訂版と、学習者自身による日本語の使用頻度と能力に関するself-assessmentです。結果はどのアセスメント方法でも非常にはっきりと出ていて、保護者が日本語を母語として話すグループ ((3) Parent Group)のみが、他の3グループとくらべて、日本語の使用頻度、使用能力に関して大きな差がみられたとのことです。(4)のLearner Groupは、だいたい高校で日本語を3年くらい勉強してきた子女だったそうですが、その人たちは、日本語にルーツがある(1)や(2)のグループとそれほど変わらない日本語の使用頻度と能力を持っているということなので、一概にに継承語子女は日本語習得に優位であるというのは言えないようです。
いわゆる継承語の3rd-generation ruleというやつで、継承語は移民3代目にはなくなるという事が言われていますが、日本語でもそれが当てはまるという事なのだと思います。こういった(1)や(2)のグループは、ハワイなどの北米の一部の地域を除いては、これまでは数は多くなかったのですが、1970年代から北米に移民してきた「新一世」の世代の子女が成人して、子供を持ち始めた2010年くらいから全米の多くで見られるようになってきました。継承日本語教育を議論するにおいて、継承日本語子女の中でも大きな違いがあることを念頭においておいた方がよいなと感じました。