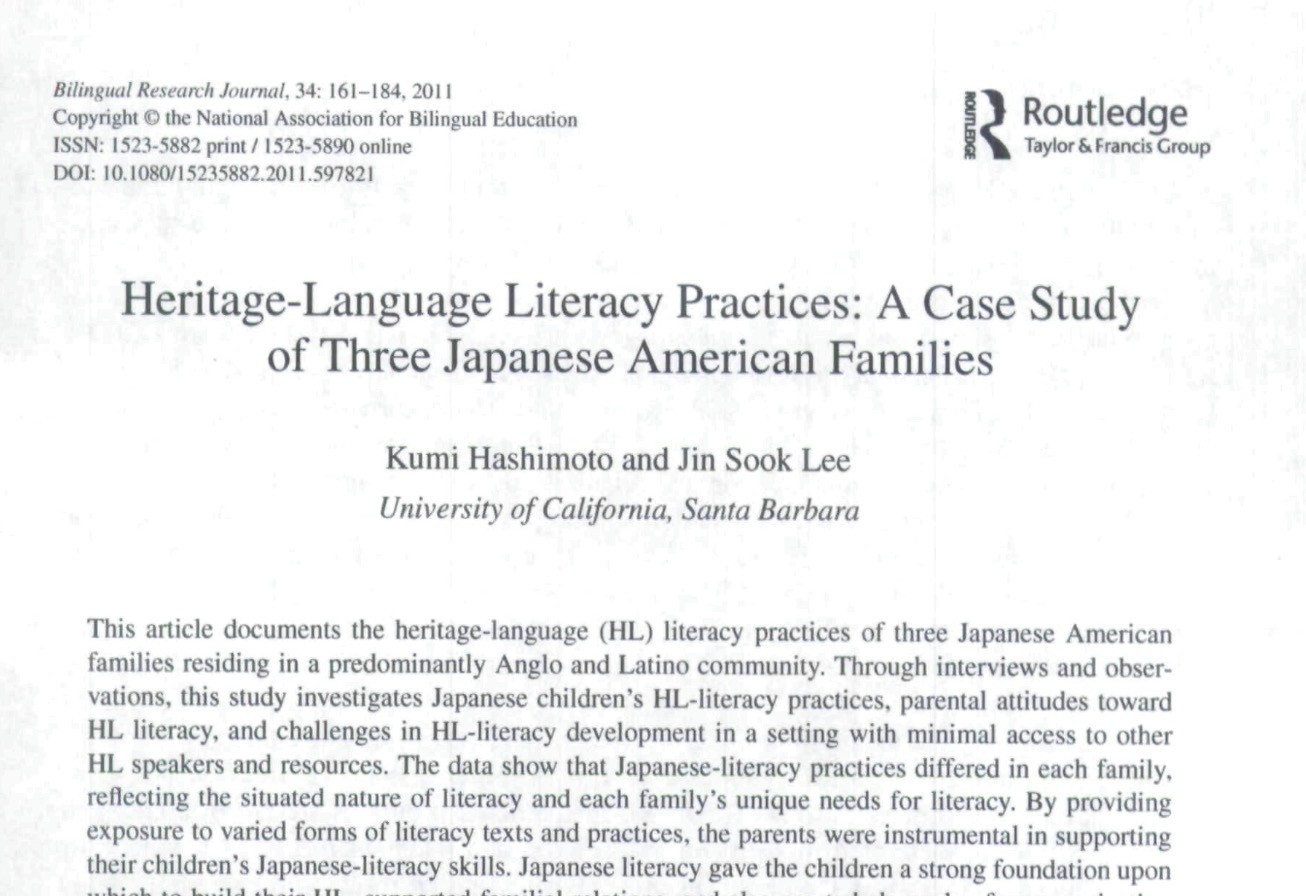- Hashimoto, K. & Lee, J. S. (2011). Heritage-Language Literacy Practices: A Case Study of Three Japanese American Families. Bilingual Research Journal, 34(2), 161-184.
アメリカ(カリフォルニア州)で、補習校や継承日本語学校がない地域で、日本語を継承語として子供に教えようとする日系アメリカ人家族を3組インタビューした研究です。場所は匿名の”Ocean City”とされていますが、著者の方々の所属地域に、最近になってようやく継承日本語学校ができたことを考えると、まあ大体どこで研究が行われたかが推測できる感じです。
大まかな内容としては、Hayashi, Maruyama, Stocktonさんという三家族の保護者とのインタビューのデータを分析したものです。三家族とも、いわゆる永住組の移民一世の日本人保護者で、アメリカで生まれた日系アメリカ人(移民二世)の子供がいて、子供の学校には日系人はいなくて、しかも、通える補習校や継承日本語学校が近郊にないという状況にあります。どの家族も永住組で継承日本語話者の日系アメリカ人の子供がいるということは共通しているのですが、配偶者(ともに日本人の配偶者の家族や、非日本語話者の配偶者の家族)や日本に帰国する頻度などは異なるそうです。
補習校、継承語学校がないので、三家族とも、継承日本語の教育は、主に保護者(特にお母さん)による家庭教育でおこなわれたとのことです。どの家族も、初めは、ひらがなを教えるドリル教材や「しまじろう」と思われる通信教材などを使ってある程度は継承語教育に成功していたのですが、子供が3-4年生になるくらいで、子供の家庭での継承語教育への興味がなくなり、また、保護者も、ひらがな以上の日本語の指導の仕方などがわからないなどの理由から、家庭での継承日本語の指導はなくなってしまったそうです。特に、「日本人だから、日本語をしないと」という理由づけによる継承語学習は、継承語子女には説得力がないものだったということです。
家庭での継承語指導はなくなったのですが、日本のマンガやアニメを見出したり、家族との手紙交換、ゲーム (Game Boy)などの使用から、日本語を自発的に使用、理解する機会は増えたとのことで、著者の方々は、ドリルや、保護者自身が受けた日本語教育をそのまま行うのではなく、継承日本語を勉強する動機づけを早いうちから考えた指導を行った方がよいと提唱しています。他方で、保護者は継承語の保持は、学校で習うような識字能力 (literacy)であるという意識があり、家庭で使用する日本語 (主に口語の日本語)が話せるようになっても、継承語保持という面では満足していないということも報告されています。
最後の方で、遠隔地に住んでいて継承語学校へ通えない人のためには、オンラインによる継承語教育の可能性についても考えるべきとのことも書かれているのですが、コロナ禍の後に急速にすすんだオンライン教育が継承日本語教育にも最近現れてきたので、この提言については今、ようやく実現されてきていると感じました。