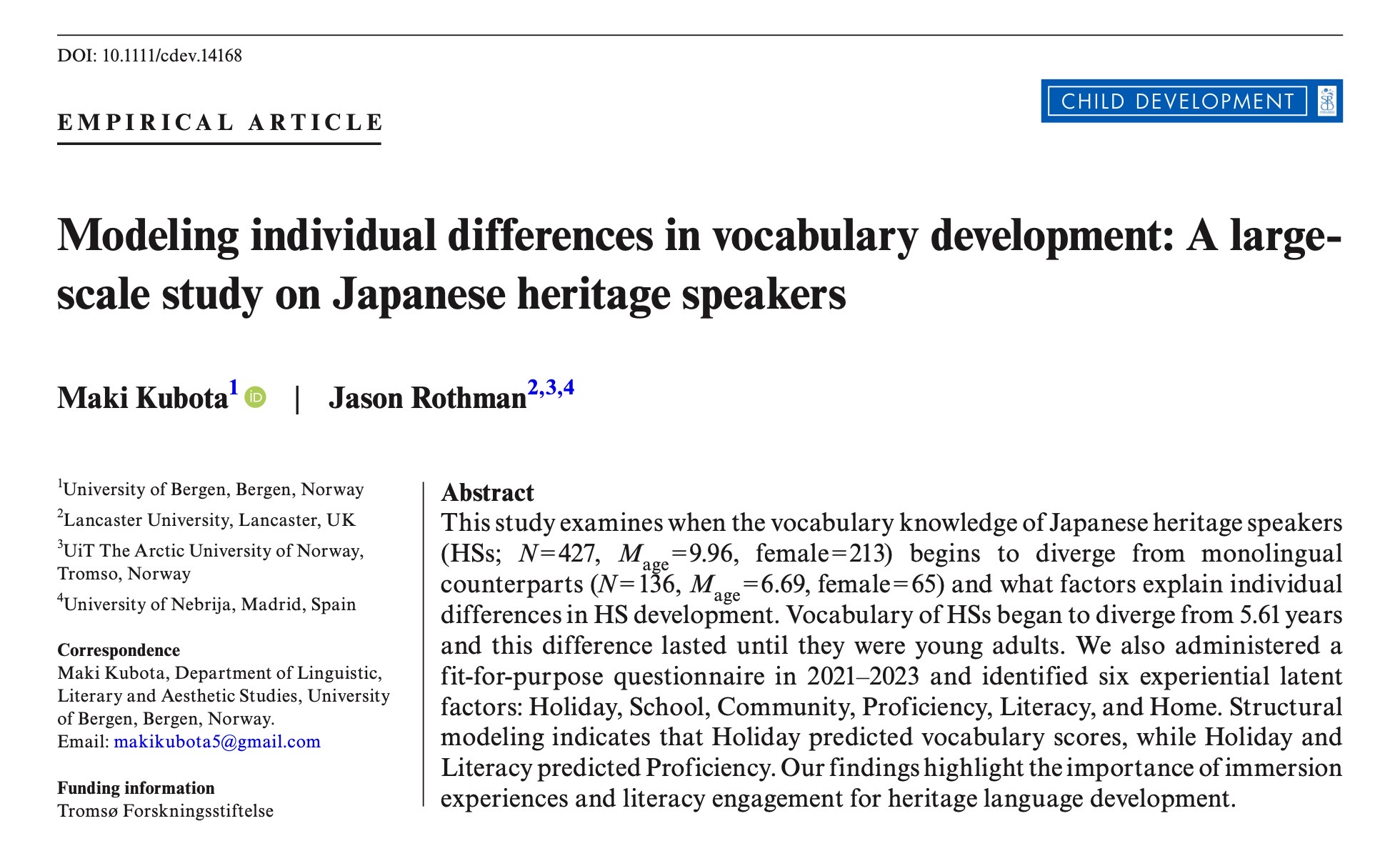- Kubota, M. & Rothman, J. (2024). Modeling individual differences in vocabulary development: A large‐scale study on Japanese heritage speakers. Child Development, 1-16.
継承日本語話者の日本語ボキャブラリー習得について、おおよそ400名の警鐘日本語話者と、150名の日本語母語話者を対象にデータを収集したものを研究した報告です。
まず、とにかく研究の対象者 (継承語子女: 427人, 母語話者: 136人)が多いのに驚きます。通常、この規模の研究ですと、アンケートなどを使ったデーター収集をすることが多いのですが、この研究は、アンケートだけでなく、PVT-Rという母語習得研究で広く使われているPPVTの日本語版を使って、個々の参加者のボキャブラリーのレベルも調べています。データー収集は、全てオンラインでGorillaというウェブツールを使って行われたということで、オンラインやテクノロジーが第二言語研究の研究手法 (methodology)に与える影響についても感じさせられる論文でした。
研究自体は、PVT-Rで集めたボキャブラリースコアと、Q-Bexという継承語話者の言語体験を調べるためのアンケートの結果を考察して、継承日本語話者のボキャブラリーと相関性がある要素を調べています。Q-Bexのアンケートは、以下の6つの要素にまとめられ、ボキャブラリーと相関性がみられたのは、「習熟度(Proficiency)」、「帰省(Holiday)」、「読み書き活動(Literacy)」だったとのことです。
- 帰省(Holiday):帰国中に他の子どもや大人と交わす日本語の使用量。
- 学校(School):学校での友だちや教師・保育者との日本語の使用量。
- 地域(Community):家庭や学校以外の地域社会での日本語の使用量。
- 習熟度(Proficiency):話す・理解する・読む・書くの自己評価による日本語能力。
- 読み書き活動(Literacy):日本語での読書・作文・宿題などの識字活動の頻度。
- 家庭(Home):保護者との日本語のやり取り量と養育者の最終学歴。
ボキャブラリーテストのスコアと、子供の自己評価による習熟度(Proficiency)に相関性があるのは当たり前なのですが、逆に、ほぼ全部のアンケート要素が、それほどボキャブラリーテストのスコアと相関性がないことに驚きます。相関性があったのは、「帰省(Holiday)」だけでした。また、「帰省(Holiday)」と読み書き活動(Literacy)は、「習熟度(Proficiency)」と相関性がみられたとのことで、ボキャブラリスコアと相関性がない「読み書き活動(Literacy)」が自己評価の「習熟度(Proficiency)」と相関性がみられるのは興味深いです。
結果的に、「帰省(Holiday)」の要素が際立っているのは、継承日本語を行いたい教育者や保護者にとっては、歯がゆい結果だと思います。著者の方もかかれていますが、一時帰国は全ての家族ができるわけでわないので、大事だとわかっていてもできない家庭は多くあるかと思います。また、学校や地域などの要素に相関性がみられなかったのは、継承語学校での教育者にとっては残念な結果です。
他方で、5-6歳くらいから継承日本語話者のボキャブラリーが母語話者のボキャブラリーが下回る(5-6歳くらいまでは、継承日本語話者も日本語母語話者もボキャブラリーには差異はみられない)とのことですので、ある意味、学校の大事さは間接的に現れているのではないでしょうか。アンケートが主観的な言語体験についての質問なので、保護者や継承語子女が気づかない社会的要素(例えば、何時間、日本語での授業を受けているかなど)がボキャブラリーに影響を与えているけれども、この研究では現れていない可能性はあると思います。